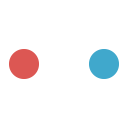お知らせ
シンポジウム報告「世界溺水防止デーに考える神奈川の海の安全」
2025.03.18
シンポジウム開催趣旨
●神奈川の海は、明治時代に我が国で最初の「海水浴場」が誕生して以来、夏季を中心とするマリンレジャー及び海洋教育の場として利用されてきた。そのための安全・安心の確保については、これまで、夏季のみ雇用される「ライフセーバー」のほか、水難救済会や海上保安庁が個別に対応してきたが、人口減少による担い手不足が顕在化する一方、海に対する人々のニーズは通年化・多様化していることから、既存制度の見直しが必要となってきている。
● 豪・ゴールドコースト市来県の機会を捉え、中長期的な海の安全確保の在り方を考えるシンポジウムを開催することにより、過去の全県的な取組(「サーフ’90」及び「かながわシープロジェクト」)も踏まえつつ、日本と豪州の比較といった視点も取り入れながら、教育啓発の強化、処遇・補償の改善、国・地方・民間の連携推進、デジタル化の検討など、中長期的な課題の解決に向けて、関係者間での機運醸成を目指した。
第2部 活動紹介
第3部
パネルディスカッション:令和時代の「海の安全」を考える
~自助・共助・公助のベストミックスに向けて~
鎌倉市長 松尾 崇 氏

神奈川県 文化スポーツ観光局長 篠原 仙一 氏

笹川平和財団 海洋政策研究所(OPRI)研究員 田中 広太郎 氏

日本ライフセービング協会理事長 入谷 拓哉 氏

- ● 「いのち輝く神奈川」の実現を目指してきた知事。その原点は、テレビキャスター時代に自ら取材・編集を手がけ、2年間のべ100回以上にわたり放送されたキャンペーン『救急医療にメス』。この企画が遂には国を動かし、「救急救命士」の制度創設にも結びつくが、当時黒岩氏の原動力となっていたのは、大切な上司を溺水事故で失った辛い経験。
- ● 人命救助への熱い思いを持ち続ける知事は、新型コロナ禍で海水浴場が閉鎖された際、日本ライフセービング協会と協力協定をいち早く締結。AIカメラやドローンなど最先端技術を駆使した監視体制である「神奈川モデル」を全国に先駆けて導入しており、今後とも市町と連携して水辺の安全確保に向け積極的に取組む姿勢。
- ● 神奈川県と34年間にわたる姉妹都市協定を有するゴールドコースト市には、43か所のビーチがあり、直近(2023年)の来訪者数は約2,000万人。オーストラリアで最大規模のビーチリゾート。
- ● ゴールドコースト市直轄の事業部門(Lifeguard Services)では、正規常勤職員42名のほか、非常勤職員等220名が在籍。監視救助だけでなく、安全教育、情報発信などビーチ関連の幅広い業務を実施。
- ● 日本との大きな違いは、大半のビーチで通年パトロールを実施していること、ビーチの安全に関する一部の自治体条例についてはライフガード自身が法執行権限を有すること。
- ● ビーチ来訪者の携帯SIMデータを分析することで、18~30歳の男性、州内の日帰り旅行者、州外からの旅行者、海外旅行者等の「高リスクグループ」を特定、ソーシャルメディアを通じて効果的な注意喚起を実施。
- ● 近年、海水浴客数や事故発生情報等について、各ビーチのライフガードが随時報告・共有できるデジタルプラットフォームを構築。ライフガード以外の公的機関による行政サービスの最適化にも活用。
- ● 「ライフセービング」の歴史が神奈川に始まって60年余り。今では30の都道府県協会、166のクラブに所属する約5,000名の有資格者が全国215か所の海水浴場で活動。離岸流や泳力不足等によって発生する事故に対して、毎年2,000~3,000件の救助を実施。
- ● 近年のライフセーバーの人手不足もあって、全国の海水浴場の5分の4で未だ有資格者が不在であるほか、マリンレジャーの通年化・多様化により、監視体制の無い海水浴場エリア外(期間外)の事故が増加するなど状況は深刻。
- ● 現状を打開するためには、以下のようなソリューションについて、地域の実情に応じて適切に組み合わせるのが有効。
- ①先端技術の導入により多くの人が海辺の利用・安全に関われる社会の創造
- ②地方公務員に対する兼業規制の緩和によるライフセーバー人材の確保
- ③公的救助機関・自治体・ライフセーバー等で構成するプラットフォームによる通年での連携・情報共有
- ④機能別消防団や日本水難救済会の救難所など既存制度の活用によるライフセービングクラブの基盤強化
- ⑤関係法令(海岸法、海水浴場条例など)の解釈見直し等による通年での安全確保を見据えた政策立案
- ● 明治22年の発足以来130年以上にわたり、公的機関と連携しながら海難救助、洋上救急(「海のドクターヘリ」)等に貢献。このうち海難救助では、毎年約500件の出動実績あり。
- ● 全国約1,300拠点で約50,000人の救助員が活動し、うち約8割が漁業関係者だが、近年はライフセーバーの救助員も登場。昨年11月には、鎌倉ライフガードを母体とする鎌倉救難所を設置。
- ● 「未然防止」も重要な課題であり、これまでも「海の安全教室」を開催。本年度からは、日本財団や日本ライフセービング協会とも連携して「海のそなえプロジェクト」を立ち上げ、海の護身術として「イカ泳ぎ」「イカポンチョ」など教育コンテンツの開発を強化。
- ● 救済会の全活動は、国の予算によらず「海で人助けをするのはあたりまえ」とのボランティア精神に頼っており、「青い羽根募金」で機材等を確保するなど、厳しい財政状況。
- ● 第三管区海上保安本部は、約450万㎢に及ぶ広大な区域を管轄(海保全体の約3分の1)。管内に23か所の事務所があり、1,481名※の職員が勤務。
- ● マリンレジャーに伴う事故対応件数のうち、直近では全国の約3割が第三管区内。その中で神奈川県内の件数は約3割に上るが、相模湾エリアでは横須賀海上保安部(106名※、10隻)と湘南海上保安署(15名※、1隻)の限られたリソースで対応。なお、事故全体の傾向として、海水浴場以外での事故が全体の約7割。
- ● 海中転落事故における死亡・行方不明者のうち、ライフジャケットの非着用率は8割超であることからも、若年層も含めて「自己救命策」を啓発することが重要。引続き、日本水難救済会や日本ライフセービング協会と連携。
※記載の人数は令和7年3月31日現在
- ● オーストラリアのように海の文化を通年で発展させるためには、安全確保の充実が必要。しかし現状では、海水浴場開設期間以外は監視体制が無いだけでなく、海保・消防・警察・ライフセーバーなど関係者の連携体制も不明確。まずは後者の点について、藤沢市の事例を参照しつつ、早急に制度設計を検討。
- ● 世間では「海離れ」が進んでいると聞くが、鎌倉ライフガードの協力で実施している「海の水泳教室」は大盛況。安全な海の楽しみ方を教育啓発する取組を拡充するべく、市でも引き続き検討。
- ● 従来型の海水浴客が減少する一方、マリンスポーツや釣りなど、海の楽しみ方は多様化。海の利用は自己責任が原則のため、危険性を含む海の特性を啓発しつつ、魅力も同時に発信できる取組について、県としても検討。
- ● ライフセーバーの人手不足が進むなか、AIやドローンなど先端技術活用の好事例を、県として積極的に横展開。
- ● 海の安全を守る現場の課題(ニーズ)と科学者の研究成果(シーズ)の「つながり」が弱い。また、学生ライフセーバーのキャリア形成に関しては、海で得た知見を活かす職業に就けず、海から離れた人生となる傾向。
- ● ECOP(Early Career Ocean Professionals、海洋若手専門家)として、ライフセーバー経験者が様々な分野で活躍しながら、現場に役立つソリューションを議論・創出できる「ゆるやかなネットワーク」が必要。
- ● ライフセーバー経験のある公務員は多数存在するが、所属先の兼業規制ゆえにボランティアで活動している状況。兼業規制を緩和し、給与支給・保険適用を確保することでインセンティブを与え、人手不足の解消を期待。
- ● オーストラリアでは、通年の職業として監視救助等に従事する「ライフガード」と、勉学や他の職業をしながら活動する「ライフセーバー」が明確に区別されており、将来の日本における制度設計で参考になる可能性。